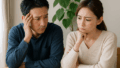【相談】自分が主夫になってもいいのか…迷いがあります
「主夫になるかもしれない自分」に戸惑う気持ち、自然なことです
相談者は…30代男性「彼女の方が稼いでる。自分が家のことをやるべきなのか迷う」
今回の相談は、30代前半の男性から寄せられたものです。
彼には長く付き合っているパートナーがいて、関係は良好。
ただ、最近彼女のキャリアが大きく飛躍し、年収も時間的拘束も増えてきた中で、彼自身は「このまま同じ働き方を続ける意味があるのか」と迷い始めているそうです。
「彼女の方が明らかに稼いでる。だったら、自分が家のことをやった方が効率的なのかなと思うこともある。でも、いざ『主夫になる』と想像すると…なぜか気持ちがざわつくんです」
「彼女を応援したい」「支えたい」という気持ちはある。
けれども、自分が“外で働かない”という選択をしたとき、無力感や不安が押し寄せてくる。
こうした葛藤は、決して珍しいものではありません。
「仕事を辞める=負け」みたいな感覚が抜けない理由
多くの男性が無意識のうちに持っている価値観に、「仕事をしていない男はダメだ」という刷り込みがあります。
これは個人の性格というよりも、社会全体が長年かけて植えつけてきた“男性役割”の価値観です。
- 男は外で働いて稼ぐべき
- 家を守るのは女性の役目
- 経済的に頼られることが、男の存在意義だ
たとえ頭では「そんな時代じゃない」とわかっていても、心の深いところでは「自分の存在価値を失うんじゃないか」と感じてしまうこともあります。
特に、今の30〜40代の世代は“ジェンダーの転換期”を生きている世代です。
古い価値観の影響も受けつつ、新しいパートナーシップの形にも向き合わなければならない。
そのギャップが、よりいっそうの迷いを生むのです。
「主夫=頼られていない」わけじゃないのに、そう感じてしまう心理
「主夫になったら、パートナーに頼られていない気がしてしまう」
こう感じる人は少なくありません。
でも、本当に「頼られていない」のでしょうか?
むしろ現代の共働き家庭において、誰かが家を“きちんと回す”ことはとても重要な役割です。
買い物・料理・掃除・洗濯・家計の管理・書類の手続き・子どもがいれば育児…これらを日々回し続けることは、立派な“生活マネジメント”であり、「家庭というチームの屋台骨を支える仕事」です。
しかし、社会的な評価が追いついていないのが現実。
「肩書き」や「年収」といったわかりやすい“価値指標”を持てないと、自分を見失ってしまいやすいのです。
このように、「主夫になりたい/なりたくない」という単純な二択ではなく、
「主夫という選択をしたとき、自分がどう感じるか?」という“内面の整理”が何より大切です。
「男が家を支えるべき」という考えはどこから来るのか?
「もし自分が主夫になったら、周りにどう思われるだろう…」
「情けない男だと思われるのではないか」
そんな不安を抱える男性は、決して少なくありません。
そもそも、なぜ「男は家を支えるべき」という考えが、これほどまでに根強く残っているのでしょうか?
ここでは、その背景と今とのズレについて考えてみましょう。
「稼ぐ=正義」とされてきた時代背景と価値観の影響
戦後の日本社会において、「家族を経済的に支えること」は男性の最大の責任であり、“正義”とされてきました。
昭和の高度経済成長期、企業戦士として懸命に働く男性像が称賛され、「夫は外で働き、妻は家庭を守る」が当たり前の家族モデルとして定着しました。
つまり、「稼ぐ=価値がある」「働いていない=役立っていない」という価値観は、社会の中に深く組み込まれていたのです。
こうした時代背景を受けて育った世代、特に今の30代後半〜50代前半の男性には、幼少期から「男は働いてなんぼ」という無言のプレッシャーが刷り込まれています。
親の背中、メディアでの描かれ方、教師や周囲の大人たちの言動…すべてがその価値観を“常識”として伝えてきました。
結果として、たとえ現代では多様な生き方が許容されつつあるとはいえ、「主夫」という選択に対し、自分の中に矛盾や抵抗を感じてしまうのです。
家事や育児を担うことの“見えにくい重さ”
もうひとつ、「主夫になること」が軽んじられてしまう理由に、“家事や育児の重さが見えにくい”という現実があります。
・買い物、料理、掃除、洗濯、ゴミ出し
・保育園の送り迎えや子どものスケジュール管理
・家計のやりくりや支払い手続き
・親族との連絡や行事の調整
これらはひとつひとつが地味で、明確な「成果」が見えにくい仕事ばかりです。
にもかかわらず、やることは多岐にわたり、精神的にも肉体的にも消耗します。
さらに、これらの“生活を支える仕事”は社会的に評価されにくく、「主夫」という立場にある男性は、「何してるの?」という問いにうまく答えられず、自分の存在意義に迷う場面が出てきます。
「何もしていないわけじゃないのに、何もしていないように思われる」
この“ギャップ”こそが、主夫という選択を難しく感じる根本なのです。
「外で働くこと」だけが役割ではないと知ることから始まる
では、こうした価値観から自由になるためには、どうすればいいのでしょうか?
まず大切なのは、「外で働くこと=唯一の貢献ではない」と、知識としてではなく“実感”として受け止めることです。
たとえば…
- パートナーが安心して働けるのは、家のことを任せられる信頼があるから
- 子どもの日常に密接に関わる存在は、家庭の安定そのものを支えている
- 体調や気持ちの変化に気づき、家族に寄り添うことも「働く」ことのひとつ
こうした視点を持てると、「主夫=後ろめたい」ではなく、「主夫=家庭を守る立派な役割」として肯定的に捉えやすくなります。
そしてもうひとつ大切なのが、「自分がどうありたいか」を言葉にして考えること。
周囲の目や社会的評価に左右されすぎず、自分たちの生活・関係性をどう築いていきたいかに焦点を当てることが、次の一歩になります。
【確認ポイント】あなたにとって“主夫”とは何か?
「主夫になるかもしれない自分」を想像して、不安や迷いが湧いてくるとき。
その感情は、必ずしも“やりたくない”という意思表示ではありません。
もしかするとそれは、
「主夫=こうあるべき」という“理想像”と、
「今の自分」とのギャップから生まれているのかもしれません。
ここでは、主夫という選択を考えるうえで、
あなた自身が何を大切にしているのかを見極める3つの視点を紹介します。
① 自分の中の「主夫像」は現実とズレていないか?
まず最初に確認しておきたいのは、あなたの中にある「主夫ってこういうもの」というイメージが、現実とどれくらい一致しているか、ということです。
たとえば…
- 「毎日掃除・洗濯・料理を完璧にこなす」
- 「育児を全面的に引き受けるのが当然」
- 「仕事を辞めたら家では100%稼働しなきゃいけない」
このような“理想的すぎる主夫像”を無意識に抱いていると、
「自分にできるのか…?」と必要以上にプレッシャーを感じてしまいます。
ですが、現実の主夫生活は、もっと柔軟です。
パートナーとの分担の仕方、外注サービスの活用、短時間の在宅ワークとの両立など、「ひとつの正解」はありません。
「全部自分でやらなきゃ」ではなく、「ふたりで暮らしをまわしていくにはどうすればいいか?」という視点に切り替えると、
主夫という選択肢に対する心理的ハードルも下がっていくはずです。
② 「周囲の目」ではなく「自分とパートナーの納得」が軸になっているか?
主夫という選択に対する不安の多くは、実は「自分の気持ち」よりも「他人の視線」から来ています。
- 「親にどう思われるだろう?」
- 「友達に言ったらバカにされないかな?」
- 「仕事を辞めたって言いづらい…」
しかし、家族をつくっていくのは他人ではなく、あなたとパートナーです。
大切なのは、「ふたりが納得して選んだかどうか」。
そこに“意味”と“安心”があるなら、他人の声は関係ありません。
たとえば、こう自問してみてください。
- 自分たちにとって、今の生活で優先したいものは何か?
- ふたりで支え合うために、どういう役割分担が一番自然か?
- その形が、長い目で見てお互いを大切にできると思えるか?
「納得して選ぶ」という感覚は、結果的にどんな不安よりも支えになります。
③ 主夫になることに対する“不安”と“本音”は何か?
最後に、自分の中にある“本音”に向き合ってみましょう。
主夫になることに対して、不安を感じるのは当然です。
でもその不安は、「自分がどうありたいのか」のヒントでもあります。
たとえば…
- 「働かなくなることへの社会的な不安」
- 「経済的にパートナーに依存してしまうことへの怖さ」
- 「自分のアイデンティティをどう持てばいいかわからない」
こうした不安を“感じないふり”をするのではなく、
あえて言葉にすることで、「じゃあ、どうしたらいいか?」を考える出発点になります。
逆に、「主夫という形も悪くないかも」と感じているなら、
それは自分にとって“新しい選択肢”になりうる可能性です。
今の時点ではっきりした答えが出なくても構いません。
大切なのは、曖昧な不安を放置せず、少しずつ言葉にしていくこと。
そのプロセス自体が、
「どんな形であれ、自分らしく暮らすための土台」になります。
【整理ワーク】自分の気持ちを言葉にしてみる
「主夫になるかもしれない」そんな可能性が現実味を帯びてきたとき、
多くの男性がぶつかるのは「なんとなく嫌だ」「自分らしくない気がする」といった、
言葉にしにくい“感情のもや”です。
しかし、こうした曖昧な感情は「言語化」することで整理され、
本当に大切にしたい価値観や、自分がまだ気づいていなかった不安が見えてきます。
ここでは、「自分の気持ち」を明確にするための3つの視点を使って、
あなた自身の中にある“引っかかり”を紐解いていきましょう。
① 「主夫になったら負けだ」と思うのはなぜ?
「主夫になる=負け」「男として終わり」「情けない」
そんな感覚がよぎったとしたら、それはどこから来ているのでしょうか?
たとえば…
- 子どものころに「男は外で働くもの」と教えられてきた
- 周囲の友人はみんな働いていて、比較してしまう
- 世間的には“養う側”が当たり前だと思われている
こうした背景を持っていると、「主夫になる=下の立場」と感じてしまうのも無理はありません。
でもここで問い直してみてください。
「“負け”って、誰に対して?」「なぜ“勝ち負け”の話になるのか?」
夫婦関係やパートナーシップは、勝ち負けではなく“支え合い”の形です。
しかも、主夫になることは「手を抜く」でも「逃げる」でもなく、
むしろ“責任ある選択”として向き合う姿勢です。
「負け」と感じてしまう自分にダメ出しするのではなく、
「なぜそう思うのか?」という問いを繰り返すことで、
思い込みから自由になるきっかけが見えてきます。
② 家のことを担う自分に、どんなイメージがある?
次に見ておきたいのは、「主夫として暮らす自分の姿」に、
あなた自身がどんな印象を持っているかという点です。
たとえば…
- 「自分には家事の才能がない」
- 「家にずっといるのは息が詰まりそう」
- 「社会とのつながりがなくなるのが怖い」
こうしたイメージが強い場合、
“主夫=窮屈で孤独な存在”という前提が心にあるかもしれません。
けれど実際には、主夫生活にも多様な形があります。
- 在宅でできる副業やフリーランスとの両立
- 家事代行サービスやデジタル家電の活用で効率化
- 地域コミュニティや趣味を通じた交流
「主夫になる」とは、“外の社会から切り離されること”ではなく、
“暮らしの役割を担うこと”にシフトするということ。
自分の時間の使い方、社会とのつながり方は、主夫であっても十分にデザインできます。
必要なのは「どう暮らしたいか?」という視点を持ち直すことなのです。
③ パートナーとどういう“生活の形”を描いていきたい?
最後に、もっとも大切な問いかけです。
「ふたりで、どんな生活を築いていきたいですか?」
これは、「主夫になる・ならない」よりも重要な視点です。
主夫という選択肢も、あくまで“ふたりの生活設計のひとつの形”。
その選択が意味を持つのは、「お互いが納得して暮らせる」ことが前提になります。
たとえば…
- パートナーが仕事に全力を注ぎたいと思っている
- 自分は家のことにやりがいを感じる瞬間がある
- 経済的にもやっていけそうな目途が立っている
そんなとき、「主夫」という選択は、
むしろ“ふたりの未来にとって最適な形”かもしれません。
一方で…
- 自分も仕事でキャリアを築きたいと思っている
- 家にこもることへの抵抗が大きい
- 経済的に不安を感じている
このようなときは、「主夫に向いていない」と感じるのも自然なこと。
要は、「選ぶか・選ばないか」よりも、
「ふたりでどういう暮らしを望むのか?」を対話することが、
これからの関係にとっての本当の意味での“土台”になります。
どんな未来が自分たちらしいのか。
その答えは、外にはありません。
「主夫になってもいいのか?」という問いの奥にある
「どんな暮らしを望んでいるのか?」という本音を、
あなた自身が少しずつ言葉にしていくこと。
それが、この迷いに“納得感”を持って向き合うための、最初の一歩になります。
【話し合いのヒント】パートナーと“新しい形”を話すには
「自分が主夫になる」という選択肢を前にしたとき、
多くの男性がぶつかるのが「世間体」と「プライド」の壁です。
一方で、パートナーとの関係を築いていく上で避けて通れないのが、
“これからの暮らし方”をどう一緒に考えていくかという視点。
ここでは、役割や価値観の固定観念をほぐしながら、
パートナーと対等に話し合うための3つのヒントを紹介します。
① 「家事をする男は情けない」という発想をまず手放す
「男が家事をするなんて情けない」
「家にいるのは、どこか負けた気がする」
そんな感情がよぎるのは、あなたが悪いのではありません。
それだけ社会が長く“男は外、女は内”という価値観に縛られてきたからです。
でも、その考えはもう、現代のリアルな生活とは一致していません。
現実には…
- 夫の方が先に退職して、主夫になる家庭もある
- 在宅ワークと家事を両立する男性も増えている
- パートナーのキャリアを支えることで充実感を得ている男性もいる
つまり、「家事=女性の役割」も、「外で稼ぐ=男の本分」も、
今や“選べる選択肢のひとつ”でしかないということ。
まずは、自分自身の中にある「古い当たり前」に気づき、
それを否定ではなく“手放す”ところから始めてみましょう。
あなたの役割を「社会のルール」で決めるのではなく、
「ふたりの暮らしに合っているか」で選ぶ柔軟さが、
これからの人生を豊かにする鍵になるはずです。
② 「家を守る」という価値も“収入”と同じくらい重要
収入を得ることは大切です。
でもそれと同じくらい、家庭を支えることにも“計り知れない価値”があります。
たとえば…
- 食事や洗濯、掃除などを通じて健康と快適を維持する
- 子どもの育成や親のケアに携わる
- パートナーが安心して働ける環境を整える
これらは一見「目立たない」「お金にならない」とされがちですが、
生活の基盤を支えている、まさに“見えないインフラ”です。
しかもそれを担う側は、時間や労力だけでなく、
「周囲の目」「孤独感」「やりがいの希薄さ」とも向き合うことになります。
だからこそ、家を守る側に回るという選択には、
むしろ「責任感」や「覚悟」が求められるのです。
「どちらが偉いか」ではなく「どちらも尊い」
この感覚をふたりで共有できたとき、
“主夫”という役割も、納得感をもって受け入れやすくなっていきます。
③ 「ふたりの幸せってなんだろう?」から始まる会話がカギ
話し合いを始めるとき、大切なのは“どこから切り出すか”です。
「自分が主夫になるかもしれないけど、どう思う?」
という聞き方は、正直ハードルが高いと感じるかもしれません。
そんなときは、こんな問いかけから始めてみてください。
「ふたりにとって、心地よく暮らせる形って何だろうね?」
この質問には、主導権争いや正解探しはありません。
あるのは「ふたりで考えよう」という対等な関係性だけです。
すると…
- パートナーが「実は仕事に全力を注ぎたい」と話すかもしれない
- あなた自身が「家事の中にもやりがいを感じる」と気づくかもしれない
- どちらが正社員かよりも「どう支え合うか」が軸になるかもしれない
“主夫”という言葉にとらわれず、「どんな暮らし方なら幸せか」を語り合うこと。
それが、ふたりにとっての「新しい形」を見つける第一歩になります。
家族の形は、時代とともに変わります。
そして、正解は「あなたたち自身」がつくっていくものです。
今の社会では、主夫という生き方が少数派に見えるかもしれません。
でも、それは「選んではいけない」という意味ではありません。
ふたりで話し、納得して選んだ形こそが、
いちばん自然で、いちばん強い関係性につながっていきます。
実例|主夫という選択に迷った男性たちのリアルな声
「主夫になる」という選択は、まだまだ少数派。
だからこそ、迷いや不安を感じるのはごく自然なことです。
ここでは、実際に「主夫という道」に向き合った男性たちの声を紹介します。
彼らの葛藤や気づき、そして今の心境は、
今まさに迷っているあなたの背中をそっと押してくれるかもしれません。
「最初は劣等感があったけど、今は納得している」──40代・元営業職
「妻のほうが昇進して、収入も安定してきたタイミングで、
自分の方は正直、キャリア的に行き詰まりを感じていました。それでも“俺が主夫になるなんて”というプライドが邪魔して、
なかなか踏み切れなかったんです。でも、冷静に考えたら、自分が家を整えて子育てを担うことで、
妻が本当にやりたい仕事に集中できるって、すごく意味のあることだと気づいて。初めは劣等感に悩んだけど、今は“ふたりで一つのチーム”という感覚で
家族と向き合えています。」
この男性のように、「役割」よりも「意味」に気づいたとき、
自分の選択に納得が持てるようになるケースは多くあります。
「“働く自分”にこだわって不機嫌だったと気づいた」──30代・フリーランス
「結婚後、妻が会社でどんどん昇進していくのを横目に、
自分はフリーランスで不安定な仕事を続けていました。でも、どこかで“男なのに”っていう気持ちが拭えなくて、
家事を手伝うにもどこかモヤモヤしていて、
気づけば家の中の雰囲気もギクシャクしていました。ある日、妻に“そんなに仕事にこだわるのって誰のため?”って聞かれて、
はっとしました。誰のせいでもなく、自分が“社会的に見て情けない”と勝手に思ってただけなんだって。
それからは、仕事も家事も“できることを精一杯やる”というスタンスになって、
不思議と家の中が明るくなったんです。」
「働く自分=価値ある自分」と思い込んでいた心の癖を見つめ直し、
“役割”ではなく“関係性”に目を向けたことで前向きになれた実例です。
「主夫として生活を支えることに誇りを持てるようになった」──50代・元公務員
「定年まで働いたあと、妻が第二のキャリアを始めたいと言ってくれて。
それなら自分が家のことをしっかりやって、妻を支えようと決めました。
最初は周囲に“尻に敷かれてる”なんて言われることもあったけど、
家を整えること、健康を管理すること、
家族の“土台”を守ることの重さを自分で実感するようになってからは、
自信を持てるようになった。今では“主夫”という肩書きにも、誇りを持って名乗れます。」
年齢を重ねてから“役割の転換”に踏み出した男性の声は、
人生のどのタイミングでも新しい形を選べるという希望を与えてくれます。
男性たちが「主夫」という選択に至った共通点とは?
これらの実例から見えてくる共通点は、以下の3つです。
- 最初は迷いがあっても、話し合いを重ねて受け入れていった
- 「自分の価値は“仕事”だけで決まらない」と気づいた
- 「支える」という役割に“意義”と“誇り”を見出した
どの男性も「社会の目」や「固定観念」に揺れながらも、
最終的には「ふたりの暮らしにとって何が最適か」を見つめ直し、
それぞれの形で答えを出しています。
主夫になるかどうかを「損得」や「男らしさ」で決めないでいい
社会の中でまだ少数派だからこそ、
「主夫」という言葉には偏見や迷いがつきものかもしれません。
でも、それはあなたの「誠実さの裏返し」でもあります。
悩むのは、真剣に生き方を考えている証拠。
迷うのは、自分の責任を放棄していない証拠。
そしてその先にあるのは、「ふたりでつくる人生の形」です。
まとめ|“主夫になること”を自分で選べる強さを持とう
「主夫になる」という選択に迷うのは、
ただ生活スタイルを変えるというだけでなく、
これまでに自分が培ってきた価値観や「男らしさ」への向き合い方を
根本から問い直すことになるからです。
しかし、その迷いの先にこそ、“本当に自分が納得できる人生”があるはずです。
ここでは、主夫になることを「自分で選べる強さ」について、3つの観点からまとめます。
「男だからこうあるべき」に縛られる必要はない
私たちは気づかないうちに、「男は仕事で家庭を支えるべき」
「家事は女性がするもの」といった“社会的な刷り込み”の中で生きてきました。
こうした価値観は、時代とともに確実に変わりつつあります。
しかし、長年すり込まれてきた考え方は、
たとえ時代が変わっても、心の奥に「正しさ」として残り続けるものです。
「自分が主夫になるなんて…」と感じる違和感は、
“あなたの中にある誠実さ”や“責任感”の裏返しであり、
それ自体が間違っているわけではありません。
けれども大切なのは、
「社会的な正解」ではなく「自分にとっての納得」を基準にすることです。
「ふたりの形」に正解があるわけじゃない
家族のかたちは多様化しています。
・共働きで家事を完全分担している夫婦
・どちらかが働き、どちらかが家庭を支えている家庭
・育児・家事・介護などで、役割が柔軟に変化していく家族も
大切なのは、「どちらが大変か」「どちらが偉いか」という話ではなく、
ふたりにとって“心地よい形”が築けているかどうかです。
主夫という立場がその一つの形であれば、
そこに誇りを持って良いし、臆する必要はありません。
「支える」という行為に、性別も優劣も必要ないのです。
「納得できる役割分担」があれば、形はどうあってもいい
人生にはさまざまなフェーズがあります。
・キャリアを優先したい時期
・家族との時間を大切にしたい時期
・健康や介護など、予期せぬ事情で役割が変わる時期
「今、自分が何を担うか」ではなく、
「その選択を自分で納得して選べるか」が何よりも大事です。
「主夫だから…」と後ろめたさを感じるのではなく、
「主夫として家庭を支えるのは、いまの自分にできる最良の貢献」と捉えられれば、
その姿勢こそが信頼や尊敬を生む土台になります。
“主夫”という選択に必要なのは、覚悟ではなく対話と柔軟さ
最も大切なのは、あなた自身が納得できていて、
その考えをパートナーとしっかり共有できているかという点です。
どんな選択であっても、不安や迷いがあって当然。
だからこそ、繰り返し話し合い、すり合わせ、
お互いに理解を深めていくことが何より重要です。
“自分の選択に自信を持てる”というのは、
「完璧に信じ切ること」ではなく、
「迷いながらも、向き合い続けること」から生まれていきます。
「自分らしい選択」でつくる、ふたりの未来
主夫になるかどうか、は
単に“仕事を続けるか・辞めるか”という問題ではありません。
それは、**「どんなふうにふたりで生きていくか」**という、
未来のかたちを決めていく問いでもあるのです。
あなたの人生を、誰かの価値観に委ねないでください。
「主夫でもいいのか?」という迷いの先には、
「主夫という選択肢を、心から選べる強さ」があります。
そしてその強さは、誰かを支える力にもなり、
自分を支える力にもなっていくはずです。