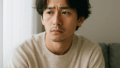【相談】自分の親と彼女の育児観が真逆で、将来が不安です
「親と彼女の意見が食い違う」…そんな不安は誰にでもある
相談者は…30代男性「親は“しつけ重視”、彼女は“自由に育てたい”派」
今回の相談者は、30代の男性会社員。結婚を考えているパートナーと将来の子育てについて話していた際、価値観の違いに戸惑いを感じたそうです。
彼の実家では「厳しさも愛情のうち」といったしつけ重視の教育方針が当たり前でした。対して、彼女は「のびのびと子どもの個性を尊重する育て方」を理想としていて、「親の言う通りにしなさい」ではなく「自分で考える力を育てたい」と話します。
「どちらが正しいのか」がわからず、将来が見えなくなる不安
自分の親に育てられた価値観も否定できない。一方で、彼女の考え方にも納得できる部分がある。どちらかを選ぶというより、どちらに寄せるべきかもわからず、将来を描くのが怖くなってしまったという相談者。
「彼女と一緒にいたい気持ちはあるけど、育児方針の違いって、結婚してから致命的な溝になるんじゃないか…?」という不安に揺れています。
結婚や育児は「ふたりだけの問題」ではなくなる現実
結婚は、当人同士だけの問題ではなくなっていくもの。とくに子どもが生まれると、「親世代」の存在感が強くなる場面も少なくありません。昔ながらの考え方が根付く親世代と、今の時代に合った育児をしたいと願うパートナー。その間に立たされる苦しさは、多くの人が経験しているものです。
ここでは、育児方針のすれ違いにどう向き合えばいいかを、整理していきましょう。
育児観の違いはなぜ深刻に感じやすいのか?
育児に関する意見の食い違いは、想像以上に心の奥に不安を残します。とくに「親 vs パートナー」という構図になると、自分のルーツと現在の関係性の板挟みに悩まされることも少なくありません。ここでは、その“深刻に感じやすくなる背景”を整理してみましょう。
「親の意見」は無視できないものとして刷り込まれている
多くの人は、育児について自分で考えるよりも先に、「自分がどう育てられたか」という体験を基準にしています。
たとえば、親が厳格だった人は「これが当たり前」と思い込みやすく、逆に放任主義だった人は「それが自然」と捉えているかもしれません。こうした“親の育児観”は、知らないうちに自分の中に根を張り、無意識のうちに「正しさ」として刷り込まれていきます。
そのため、パートナーの意見が親と大きく違うと、まるで「自分の育ちを否定されたように感じる」ことすらあるのです。
「子どもにとって何が正解か」が見えない不安
そもそも育児に「正解」はありません。ですが、子どもの人生を左右する重大なテーマだからこそ、「これでいいのか?」という不安がつきまといます。
「しっかりしつけた方がいいのか」「自由に育てた方が自立できるのか」――どちらが良いのか判断できず、相手の育児観に対しても疑問を抱きやすくなります。
相手を否定したいわけじゃないのに、「なんでそんなやり方なの?」という気持ちがにじみ出てしまい、すれ違いが深まっていくこともあります。
「育て方=価値観の衝突」になってしまいやすい理由
育児観の違いが深刻になる背景には、「子育ての話」=「価値観そのもの」と捉えられやすい点があります。
「子どもにどう接するか」は、その人の人生観や人間関係の築き方、さらには「何を大事にしているか」という本質的な部分と直結していることが多いのです。だからこそ、「やり方が違う」と感じたとき、それは単なる意見の違いではなく、「この人と根本が合わないのでは?」という不安につながってしまうのです。
しかし、それは“相手の価値観を理解するチャンス”でもあります。次章では、「本当にズレているのか」を冷静に確認する視点をお伝えしていきます。
【確認ポイント】“違い”はどこにある?なにがズレている?
パートナーとの間に育児観の違いを感じたとき、「合わないのかも…」と早合点するのはもったいないかもしれません。実は、“全体的に合わない”わけではなく、ズレているのは一部分だけということも多いのです。
ここでは、その“違い”がどこにあるのかを整理するための3つの確認ポイントを紹介します。
①「厳しさ」や「ルール」の捉え方に差がある?
育児において、「しつけ」や「ルールを守らせる」ことを重視するか、それとも「子どもの自主性」や「のびのび育てる」ことを重視するかは、人によって大きく異なります。
たとえば、相談者のように「親は厳しく育てる派」「彼女は自由を大切にする派」のように分かれていると、そもそも「子どもにどう接するのが愛情か?」という前提がズレていることになります。
この違いは、「何を大切に育てたいか」が見えてくるヒントにもなります。単に“甘い・厳しい”という軸ではなく、「子どもに何を伝えたいのか?」という視点で考えると、意外と共通する思いがあることに気づけるかもしれません。
②「親の意見」はどこまで優先したいと思っている?
もう一つ見逃せないのが、自分の親(ときに義両親)の意見を“どこまで取り入れたいと思っているか”です。
「うちの親は経験者だから」とその意見を当然のように採用したいと考えている場合、パートナーは「自分の考えが尊重されていない」と感じてしまうかもしれません。
逆に、「親の意見も一理あるけど、ふたりで決めたい」と思っている場合は、それを明確に伝えることで不安を取り除くこともできます。
ここで重要なのは、「誰の価値観をベースに子育てをしたいのか?」を話し合ってすり合わせることです。両親の意見を参考にすることと、丸呑みすることは違います。
③「どんな子に育ってほしいか」のイメージは近い?
最終的に育児観のすり合わせで大切なのは、「どんな子どもに育ってほしいか」という未来のビジョンです。
・思いやりのある子になってほしい
・自分の頭で考えて行動できる子に育てたい
・失敗しても自信を持てる子になってほしい
こうした願いを言葉にしたとき、方法論(しつけの仕方や日々の接し方)に違いがあっても、「目的」は近いことが多いのです。
つまり、意見が分かれているのは“手段”の部分だけで、実はふたりとも「子どもに幸せになってほしい」というゴールは同じ──ということも十分にあり得ます。
【整理ワーク】自分が育児で「大事にしたいこと」は?
「親と彼女、どちらの育児観が正しいのか?」と考える前に、一度立ち止まって、自分自身の価値観を見つめ直してみませんか?
どちらかの意見に振り回される前に、“自分はどうしたいのか”を言葉にしておくことで、話し合いの軸が明確になります。
ここでは、自分の育児観を整理するための3つの視点を紹介します。
① 自分はどんな風に育てられて、どう感じてきた?
まずは、自分自身の子ども時代を振り返ってみましょう。
・親は厳しかった? それとも自由に育ててくれた?
・その中で「ありがたかったこと」「辛かったこと」は?
・今の自分に影響を与えていると感じる子ども時代の出来事は?
過去の体験を思い出すことで、「自分が子どもに何をしてあげたいのか」「何を避けたいと思っているのか」が自然と見えてきます。
たとえば「親はよく叱ってくれたけど、それで自信をなくした」という思いがあるなら、自分は“もっと認めてあげる子育て”をしたいと感じているかもしれません。
② 親の考えに共感できる部分・疑問がある部分は?
親の意見や価値観をすべて否定する必要はありません。むしろ、長年育児を経験してきた立場だからこそ、学べることも多いでしょう。
・「しつけの厳しさ」や「礼儀」へのこだわり
・「早寝早起き」や「生活習慣」を大切にする姿勢
・「親の背中を見せて育てる」という考え方 など
その中で「なるほど」と思える部分と、「でも、今の時代には合わないかも…」と違和感を覚える部分を整理してみましょう。
親世代と自分たちの世代では、育児を取り巻く環境や情報がまったく違います。違いがあるのは当然です。大切なのは、その違いを客観的に見つめる姿勢です。
③ 彼女の考えに対して納得できる点は?不安な点は?
次に、パートナーの育児観を改めて“丁寧に言語化してみる”ことが重要です。
・子どもを「自由にのびのび育てたい」という考え
・「失敗も含めて経験して学ばせたい」という価値観
・「親は管理者ではなく、伴走者でいたい」という姿勢
これらに共感できる点がある一方で、「それだと甘やかしにならないか?」「社会で通用するか不安」と感じる部分もあるかもしれません。
ここで大切なのは、「納得できる部分」だけでなく「不安に感じる部分」も自分の中で正直に認めてあげること。その両方を整理しておくことで、対話の中でも冷静に意見を伝えやすくなります。
【話し合いのヒント】“親の考え”と“ふたりの方針”をどう調整する?
育児において、親(実家)の意見はつい大きな存在になります。「親が言うならそうすべき?」「でも彼女の意見も大切にしたい…」と板挟みになる人も少なくありません。
ここでは、親の考えを無視せずに、ふたりの納得できる育児方針を作るための視点を紹介します。
「親の言うこと=絶対」ではないと自覚する
日本の家族文化では、親の言うことを「大切にするべき」という意識が強く根づいています。特に「子育て経験がある親の意見は正しい」と感じる方も多いでしょう。
しかし、親の考えが必ずしも「今の時代に合った正解」とは限りません。
・親は“しつけ重視”だったけど、それが正しいとは限らない
・昔と今では教育の常識や価値観が大きく違う
・夫婦それぞれが「納得して進められる」ことの方が重要
大切なのは、「親の考えを取り入れるか否か」ではなく、「ふたりの子どもにとって何がベストか?」という軸で考えることです。
「育児の方針」はふたりの“納得”がベースになる
親の意見に振り回されて、パートナーとの信頼関係が崩れてしまっては本末転倒です。
育児方針は、“親のため”ではなく、“これから親になるふたりのため”に決めるもの。そのためには、以下のようなスタンスが必要です。
- 親の意見も聞いた上で、ふたりでじっくり話す
- 「自分たちに合うスタイルは何か?」を探す
- 「彼女に我慢させることがないように配慮する」意識を持つ
ときには、親の価値観とぶつかる選択をすることもあるでしょう。しかし、「ふたりで話してこう決めた」と堂々と言える関係であれば、その選択は揺るぎません。
「親を否定する」ではなく「自分の価値観」を整理して伝える
親の考えと違う方針を取るとき、「否定された」と親が感じてしまうこともあります。だからこそ、伝え方が大切です。
たとえば…
×「そのやり方、古いよ」
◯「今はこういうやり方があって、僕たちはこの方法を試してみたい」
×「それは間違ってる」
◯「子どもにはこう育ってほしいから、今はこの選択をしたいと思ってる」
相手を否定せず、自分たちの考えを“丁寧に言語化する”ことで、親との関係性を崩さずに方針を伝えることができます。
実例|「親とパートナーの育児観」で悩んだ人たちの声
「親と彼女(妻)の意見が違う。どうしたらいいのかわからない…」という悩みは、実は多くの人が経験しています。ここでは、実際に葛藤を抱えた人たちがどのように向き合い、乗り越えていったのかをご紹介します。
「親に強く言えなかったけど、勇気を出した」ケース
30代前半・男性(第一子出産直後)
「うちの親は“泣いたら抱っこするな”ってタイプで…。でも妻は“赤ちゃんの気持ちに寄り添いたい”という育児方針。間に立つのが本当に苦しくて、最初は妻にも親にも気を使ってばかりでした。
でもある日、妻が泣きながら“もう無理”って言ったんです。そこでやっと、自分の立場や親への遠慮より、“今の家族”を守ることが優先だと気づきました。
勇気を出して親に『僕たちはこうしたい』と伝えたら、最初は驚かれたけど、少しずつ理解してくれるようになりました。」
💡 ポイント: 親に「NO」を伝えるのは勇気がいること。でも、それが“自分たちの家族”を守る第一歩になることもあります。
「育児方針を“ふたりの軸”に切り替えた」ことで関係が安定した例
20代後半・男性(子育て1年目)
「僕の親は“食事は残さず食べるべき”という考えで、子どもにもしっかりしつけようとする。でも妻は“無理して食べさせたくない”というタイプ。
最初はどちらの言い分も分かる気がして、自分の中でもモヤモヤしてたけど、ある日『どうしても納得できない』と妻に言われて気づいたんです。
それからは、“自分たちがどうしたいか”を最優先にするようにしました。親には『僕たちはこのやり方でやってみたい』と伝え、あとは感謝を忘れずに接するように意識しています。
方針が定まったことで、家の中の雰囲気も安定しました。」
💡 ポイント: “誰の方針が正しいか”ではなく、“今の家庭に合う方針かどうか”で決めることが鍵。
「親をうまく巻き込みながら、バランスを取った」成功例
40代男性(第二子育児中)
「親が“昔ながらの育児”で、手伝ってくれるのはありがたいけど、細かい指摘が多くて妻がストレスを感じてました。
そこで、“お義母さん、手伝ってくれてありがとう。最近はこういうやり方もあるみたいです”と、親の協力を否定せず、新しい情報を“共有する”形で伝えるようにしました。
また、親が関わるときは“お願いベース”にして、妻と一緒に無理のない距離感を作るようにしています。
結果、親も“頼られている”と感じられて、関係がうまくいくようになりました。」
💡 ポイント: 親を「排除する」ではなく「味方にする」視点が、家族関係を円滑にする鍵になることも。
まとめ|“誰の価値観で育てるか”を、ふたりで決めていこう
親との関係も大切。パートナーとの関係も大切。でも、育児において一番重要なのは、これから「親」になるふたりが、自分たちで納得できる方針を持てるかどうかです。
ここでは、育児観の違いで悩んだときに立ち返りたいポイントをまとめます。
「親の意見=正解」ではない
親の育児経験は確かに貴重です。しかし、それは「その時代の子育て」の経験にすぎません。
- 社会や価値観は変わる
- 夫婦の関係性も変化している
- 子ども一人ひとりに合う育て方も違う
親の意見は“参考”にすることができても、“唯一の正解”ではありません。自分たちの子どもを、誰の価値観で育てたいか?——そこをしっかり見つめることが必要です。
「彼女と一緒に育てる」未来をどう築くかが大切
彼女(妻)は、これから“あなたと一緒に親になる”パートナーです。
- 意見がぶつかったときこそ、どう向き合えるかが問われる
- 一緒に悩み、考え、選択していく経験が「ふたりの軸」をつくる
- 子どもの将来にとっても、協力し合える親の姿は何よりの支えになります
育児は、正解がないからこそ「一緒に選んだ道」が子どもにとっての安心になります。
「話し合える関係性」こそが、子育てにおいても一番の土台
育児において、正解よりも大切なのは、「話し合える関係性」を育むことです。
- 疑問や違和感を言葉にできる
- 意見が違っても、一緒に折り合いをつけていける
- 相手の想いも自分の想いも大切にできる
これらができる関係性は、子育て中のあらゆる困難を乗り越える“力”になります。
「親と彼女、どちらの意見を選ぶか」ではなく、ふたりでどう決めるかが大切です。誰かに合わせるのではなく、ふたりの子どもに合う育児を、話し合いながら見つけていきましょう。
次に必要なのは、あなた自身が「自分たちらしい子育てってなんだろう?」と問い直すことかもしれません。