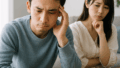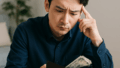【相談】共働きでも家計管理は自分?金銭バランスに悩んでいます
「共働きなのに家計管理は全部自分」…その悩み、よくあることです
相談者の声:
「30代前半・共働きの会社員です。結婚して2年目ですが、家計の管理はすべて僕の担当。最初は自然な流れでしたが、最近“なんで全部自分なんだろう”とモヤモヤしてきて…。彼女は悪気はないと思うけど、家計簿も見ていないし、お金の話になると『任せるね』で終わってしまうんです。共働きって、もっと対等なはずじゃないのか?と悩んでいます。」
このように、「家計をすべて任されている」「話し合いができていない」と感じている男性は少なくありません。
結婚・同棲を機に浮かび上がる“家計の偏り”
恋人同士の頃は「割り勘」や「その場ごとの支払い」で済んでいたとしても、
結婚や同棲を機に“家計をどう管理するか”という課題が浮き彫りになります。
特に共働きの場合、次のような流れで偏りが生まれがちです。
- 家計簿をつけていた方がなんとなく担当に
- 契約や引き落とし口座をひとまず片方に集中
- お互い忙しく、話し合いの時間を取らずにスタート
こうして始まった「家計担当」が、いつの間にか固定化されてしまうことはよくあります。
「なぜ自分だけ?」と感じてしまう背景
不満が募る原因は、「物理的な手間」だけではありません。
- 自分ばかりが支出を把握している
- 相手は貯蓄や将来設計に無関心
- 支払いの相談もなく自動的に任される
このような状況が続くと、**「共同生活なのに、自分ばかりが責任を負っている」**という感覚になってきます。
そして、「彼女(妻)はなぜ協力しないんだろう?」「自分の負担に気づいていないのでは?」といった疑念につながり、お金のことが“関係性のズレ”として意識されるようになるのです。
「任されている」ではなく「丸投げされている」現実
「家計を任されている」といえば聞こえはいいかもしれません。
でも実際は、“信頼”というよりも“無関心からの丸投げ”に近いケースも多く見受けられます。
- 相手が数字に弱いから仕方ない?
- 管理されるのが苦手な性格だから?
- 忙しいから後回しにしているだけ?
どれも一理あるように思えますが、2人の生活に関わる大事なお金の話を、片方がすべて背負うのは不健全な状態です。
共働きである以上、金銭面でも対等な意識と分担が必要です。
それができていないと、どんなに関係が良くても、ふとした瞬間に「不公平感」が顔を出してしまうことがあります。
“共働き夫婦の家計管理”でよくある不満とズレ
共働きであっても「お金の管理」はどちらか一方に偏るケースが少なくありません。
表面的には「任せた方がスムーズ」「信頼してるから」といった理由が語られるものの、
実際には不満やストレスが“じわじわと積もる”状態が多く見られます。
「稼ぎの差」よりも「意識の差」が大きなストレスに
家計の分担で問題になるのは、「収入の差」そのものより、
お金に対する意識のズレのほうが圧倒的に大きなストレスになります。
たとえば…
- 自分の方が収入が多いからと、すべての生活費を出す流れになっている
- 収入差はほぼ同じなのに、管理・貯金・請求まで任されている
- 相手は「何にいくら使っているか」を把握しようともしない
このような状態が続くと、ふとした瞬間に
「このままのバランスでずっと生活していくのか?」という不安が浮かびます。
“どちらがどれだけ出しているか”ではなく、“気持ちよく暮らせているか”が大事。
そこに無理があると、少しずつすれ違いが生まれていきます。
「お金に無関心なパートナー」がもたらす見えない負担
パートナーが「お金の管理が苦手」「家計に無頓着」なタイプの場合、
もう一方が**“精神的・実務的な両方の負担”を背負うこと**になります。
たとえば…
- 請求書、支払い、口座管理などの“事務作業”をすべて任される
- 収支バランスを把握していない相手との意思疎通が難しい
- 「何にいくら使ってる?」と聞くだけで嫌な空気になる
こうした状況が続くと、「お金のことを全部任されている」という現実が
大きなストレスになり、生活そのものに疲弊感が出てきます。
「共働き=フェア」にならない原因とは?
よく「共働きならフェアでしょ」と言われがちですが、
実際の暮らしの中では、“フェア”と“対等”は同じではありません。
よくあるズレの原因は以下のようなものです:
- 金銭管理の労力まで「見えない労働」として評価されていない
- 収入が同程度でも、支払いをするのは片方だけになっている
- 話し合いの場が持てず、初期設定のまま流れ続けている
つまり、「お互いの認識のズレ」がフェアな状態を妨げているのです。
そして、そのズレを放置してしまうと、
お金だけでなく、関係性全体に“信頼のひずみ”が出てくることもあります。
【整理ワーク】あなたの「負担感」の正体を見える化する
「自分ばかりが家計管理をしている気がする」「なんだか損しているように感じる」
――このような“負担感”には、必ず見えない理由があります。
まずはその正体を「見える化」してみましょう。感情だけでなく、具体的な状況を整理することで、モヤモヤが言語化しやすくなり、パートナーとの対話の材料にもなります。
① 管理している“項目の多さ”をリスト化する
家計管理と言っても、その中にはさまざまな細かい作業が含まれています。たとえば以下のようなもの:
- 家賃・光熱費・通信費の支払い管理
- クレジットカードや引き落とし口座の管理
- 共通の買い物や日用品の精算
- 家計簿の記録、予算の立て直し
- 確定申告や税金関連の確認
- 保険や貯蓄の見直し・管理
このように、「一括で任されているつもりはないけれど、結果的に全部自分」になっていることも多いのです。
✅ ワーク:
紙でもスマホでもOKなので、「自分がやっている家計関連の作業」をすべてリストアップしてみましょう。
②「金額」より「時間・労力」が偏っていないかを確認
共働きカップルによくあるのが、「金額では割り勘なのに、実務の負担がどちらかに集中している」というパターンです。
たとえば:
- 彼女も収入を出しているが、支払いの確認や振り込みはすべて自分
- 家計簿アプリの入力、月末の集計も任されている
- 家電や保険の見直しなど、将来的な計画も一人で進めている
これらはすべて**「目に見えにくい家事=メンタル家事」として蓄積**され、
**時間と労力に見合わない“隠れたストレス”**になります。
✅ ワーク:
先ほどのリストに対して、それぞれ「どのくらいの時間・手間がかかっているか」「疲れや面倒に感じているか」などを◎○△でチェックしてみましょう。
③ 気になる「感情面のモヤモヤ」も書き出してみる
負担感の背景には、次のような感情的な要素が潜んでいることが多いです:
- 「自分ばかり頑張っている気がする」
- 「ちゃんと向き合ってくれないと感じる」
- 「このまま一生この役割なのかと不安になる」
これらを言葉にしないままでいると、じわじわと関係性に悪影響を与えることもあります。
✅ ワーク:
「なんでこんなにモヤモヤするんだろう?」と感じる瞬間や、相手への違和感・期待・諦めなどを率直に紙に書き出してみましょう。
完璧である必要はありません。“気持ちの棚卸し”をするだけでも、自分自身が何に悩んでいるのかが明確になります。
【話し合いのヒント】不公平感を伝える3つの工夫
「家計の負担が一方に偏っている」と感じたとき、
それをパートナーに伝えるのは簡単ではありません。
「責めていると思われそう」
「空気が悪くなるのが怖い」
――そんな思いから、つい我慢してしまう方も多いのではないでしょうか。
でも、話さなければ状況は変わりません。
ここでは、パートナーとの対話を円滑に進めるための3つの工夫を紹介します。
「不満」ではなく「提案」の形で伝える
人は「責められている」と感じた瞬間、防衛的になりがちです。
たとえば「どうして私ばっかり?」という伝え方だと、相手も身構えてしまいます。
そこで大事なのが、「改善の提案」として伝えること。
×:なんで全部私がやらなきゃいけないの?
〇:一緒に家計管理のバランスを考えたいんだけど、どう思う?
このように話せば、相手も「自分ごと」として受け取りやすくなります。
「負担の見える化」で“感情論”を避ける
先の整理ワークで作成したリストは、まさに話し合いの武器になります。
感情だけで「疲れた」と言うよりも、
- 管理している項目の多さ
- 時間的・精神的な労力
- 現状の不均衡
これらを**“数字”や“実例”として示すことで、冷静な話し合いがしやすくなります。**
たとえば:
「私がやっていることを書き出してみたら、意外と多くて。これ、どう思う?」
「週末だけでも、一部の支払い管理をお願いできる?」
「事実」をもとに話すことで、責める形になりにくく、協力しやすい空気をつくれます。
「将来のライフプラン」から逆算して話す
今の家計管理の話に留まらず、
将来のライフスタイルやお金の計画から逆算して考えるのも有効です。
たとえば:
- 子どもができたらどう分担していくか
- 住宅購入や老後の資金管理をどうするか
- もしどちらかが病気や転職になったら?
こうした未来の話を持ち出すことで、相手も真剣に考えやすくなります。
「今のままでは将来が不安」という視点なら、協力の必要性が明確になるからです。
実例|“金銭バランス”に悩んだ男性たちの声
共働きが当たり前になった現代でも、
家計管理の負担がどちらか一方に偏るケースは少なくありません。
特に「自分ばかりが家計を背負っている」と感じている男性は多く、
その背景には、話し合い不足や役割の固定観念、無意識の丸投げなどが潜んでいます。
ここでは、実際に金銭バランスに悩んだ男性たちの声を紹介します。
「見える化」でパートナーも気づいてくれたケース
「もともと自分が家計管理が得意だったから、なんとなく全部やってたんです。でも忙しくなるにつれ、負担感が大きくなって。
試しに“今自分がやっていること”をリストにして彼女に見せたら、“こんなにやってくれてたの?”って驚かれて。
それからは、家計簿の入力と支払いは彼女が担当してくれるようになりました」
このケースのように、相手が悪気なく“気づいていなかった”だけということもあります。
可視化は、責めずに気づきを促す有効な手段です。
「共働きでもお金の話をしない関係」が招いたトラブル
「同棲を始めたとき、自然と僕が家賃や光熱費を立て替えてたんです。
でも彼女は『いつもありがとう』とは言うけど、具体的な負担の分担については話そうとしない。
結局、“感謝されてるだけで、当然だと思われてる?”と不満が溜まって、ケンカになりました。
今思えば、早い段階で“お金の話”をすべきだったなと思います」
お金の話は“タブー”ではなく、現実を共有するための土台。
話し合わないままだと、気づかぬうちに信頼が削られることもあります。
「交代制」「分担制」に切り替えてラクになった例
「最初はずっと自分が管理してたけど、仕事が忙しくなって限界を感じて。
彼女と話して、“2ヶ月ごとの交代制”にしたら、負担がぐっと減って気持ちが軽くなった。
家計簿アプリを共有するようにしたら、“見える化”もできて、お互いの意識が高まったのもよかったです」
このように、「ずっと誰かが背負う」形ではなく、交代や分担で柔軟に設計することでストレスが軽減されるケースも多くあります。
“共働き=自立”ではない。2人で管理する体制づくりを
「共働きなんだから、お互い自立しているはず」
そう考える人は多いかもしれません。
でも現実には、収入が別でも、家計の管理はどちらかに丸投げ、
あるいは「相手が何にいくら使っているかまったく知らない」なんてケースも珍しくありません。
本当に自立している関係とは、**それぞれが“孤立”することではなく、
生活の現実を“共有し、連携できること”**なのです。
「どちらかに任せる」ではなく「一緒に把握する」姿勢
たとえ片方が家計管理を担当するにしても、
もう一方が**「任せきり」ではなく、“現状を把握する姿勢”を持つことが大切**です。
- 今月どのくらいの支出があったのか
- 貯金は計画通りに進んでいるか
- 将来的にどんな出費が予想されるか
こうした話題を日常的に共有できているカップルほど、結婚後も信頼関係を築きやすい傾向にあります。
得意不得意の役割分担はアリ。でも丸投げはNG
「数字に強いから自分が管理している」
「手続きが得意なほうが支払いをしている」
――そんな役割分担はまったく問題ありません。
大切なのは、“協力体制”になっているかどうか。
たとえ任せる場面が多くても、以下のような姿勢があるだけで不公平感は減ります:
- お互いの状況を確認し合う
- 月末やボーナス時に一緒に振り返る
- 大きな出費は一緒に相談して決める
逆に、「全部お願いね」と投げっぱなしにする態度が続くと、
片方にばかりストレスが溜まり、やがて関係にも影響を及ぼします。
「お金の話」が自然にできる関係性が理想
「お金のことって話しにくい…」という空気は、
カップルの間でこそ根強く残っています。
でも、お金は生活の土台であり、
それを共有できる関係性は、信頼と安心を生みます。
- 「これって高いかな?」と気軽に話せる
- 「将来こういう暮らしがしたい」と夢を共有できる
- 「今ちょっとピンチかも」と素直に言える
そんな関係性があれば、たとえ家計が苦しい時期でも、
“ふたりで乗り越えよう”という感覚を持ち続けることができます。
まとめ|“なんとなく”の家計管理は卒業しよう
共働きなのに、気づけば家計管理を一手に引き受けている――
そんな状況に、モヤモヤを感じている人は少なくありません。
でも、その違和感を「自分がしっかりしなきゃ」と無理に押さえ込んでしまうと、
気持ちだけでなく関係そのものにも“ひずみ”が出てくる可能性があります。
結婚や同棲といった大きな転機を迎える今だからこそ、
“なんとなく”のまま進めてきた家計の形を、一度立ち止まって見直すことが大切です。
「家計の偏り」は早めに向き合った方がいい理由
お金のことは後回しにしがちですが、
「今」はまだ調整しやすいタイミングでもあります。
- 役割の分担が決まってしまう前
- 気持ちに余裕があるうち
- 「やっぱり違った」と後悔する前
家計の偏りや不公平感に早めに気づいて行動することで、
将来のストレスやトラブルを回避できるのです。
「気持ちの不公平感」が消えれば関係も変わる
お金の問題は「金額」だけでなく、
その背後にある**「感情の偏り」**が関係に影響を与えます。
- 「私ばかりが背負っている」
- 「感謝されていない気がする」
- 「相手に理解されていない」
こうした気持ちは、話し合いと工夫次第で変えられます。
そして気持ちのバランスが整うことで、2人の関係にも温かさや安心感が戻ってくるのです。
2人の暮らしをつくるのは、気持ちもお金も“共有”から
家計管理は、生活の一部にすぎません。
けれどそこには、**「信頼」や「未来への意識」**が表れます。
- 自分ひとりで抱えるのではなく、
- 相手に全てを任せるのでもなく、
- 一緒に考えて、話して、決めていく。
それが、“2人で暮らす”ということの本当の意味ではないでしょうか。
もしあなたが今、「なんで自分ばかり?」と感じているなら、
その気持ちは、これからのパートナーシップを見つめ直すきっかけになるはずです。
無理せず、我慢せず、
**2人にとって心地よい“家計のカタチ”**を探していきましょう。